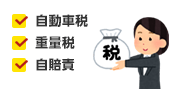自動車エンジンの長い歴史:後編~エンジンの話(3)~
エンジンの歴史を見ていく上で、必ず出てくると言ってもよさそうな日本。しかし、日本の話が大きく出てくるのは、20世紀、しかも戦後になってからのことです。というのも、日本は鎖国の影響もあり、機械を作るということ自体が難しい環境でもありました。
この後編では、日本も徐々に登場する20世紀、特に戦前までの歴史を見ていきます。

車のエンジンスタートボタン
今となっては当たり前のエンジンの始動…鍵を入れて回す、あるいはスタートボタンを押すだけでエンジンがかかるようになっています。しかし、20世紀前半までは命がけの作業だったのだそうです。というのも、今のような自動スタートができず、クランク棒と呼ばれる棒を回してエンジンをかけなければなりませんでした。
クランク棒とは、エンジン内部のクランクシャフトに直接つながっている物で、内燃機エンジンの開発初期の頃にはエンジンを始動させるための大切なものでした。現在の内燃機型エンジンにもクランクシャフトは使用されていますが、クランク棒を回してエンジンを始動させるようなエンジン始動方法はありません。今では鍵(スタートキー)を回したり、スタートボタンを押したりする動作です。

赤い矢印の先にクランクシャフトがある

緑の矢印の先が、フライホイール
内燃機エンジンの動作を一般的な4サイクルエンジンで、端的に説明すると、
① 吸入:ピストンが下がり、吸気バルブから燃料と空気の混合気を燃焼室に吸入
② 圧縮:クランクシャフトでピストンを押上げてシリンダー内部の混合気を圧縮
③ 燃焼:圧縮混合気に火花で点火。ピストンを燃焼の爆風で押下げクランクシャフトを回す
④ 排気:ピストンが上がり、排気バルブから燃焼ガスを排出
といったサイクルを連続して行う事で、クランクシャフトを回転させます。回転したクランクシャフトの連動により、1気筒内のピストンが2往復する間に1回の燃焼と1回の排気をします。それを複数の気筒で連続しておこなうことでエンジンは動いていますが、ではエンジン始動時に、① 吸入の段階でピストンを下げるためのクランクシャフト回転を得るにはどうしたら良いのでしょうか?
その最初の回転を、手動で回すクランク棒で、直接クランクシャフトを回転させて行っていたのです。しかし回すのにはコツが必要で、上手くいかないとエンジンがかかりませんでした。それどころか、棒が逆回転をすることで思わぬケガをすることも多いという問題がありました。最悪の場合は、命を落とす人までいたと言います。
今ではまったく考えられない話ですが、当時はそれが一つの大問題だったのです。
その問題に目を向け、解決しようと考えたのが、アメリカの高級車リンカーンやキャデラックを立ち上げた張本人、ヘンリー・マーティン・リーランドです。そして、その意思を受け、発明家のチャールズ・フランクリン・ケッタリングが電動モーターを使ったセルフスターターを開発します。
1912年にはその装置がキャデラックに装備されて販売、女性用のオプションとして大人気を博しました。その後は、当時大人気だったT型フォードにも1917年から装備されるようになり、命がけのエンジンスタートから解放されたのだそうです。
同時に、そのエンジン始動装置、セルモーターの発明により運転が大衆化、自動車普及の一因になったとされています。

セルモーターのギアでフライホイールを回す

回ったフライホイールはクランクを回す
自動車が普及するようになると、その性能を競い合い、自動車レースが開かれるようになりました。また、貴族や富豪が飛びつくような高級車が開発され、その性能はどんどん上がっていくことになります。
フランスでは1906年に第一回のACFグランプリを開催、まだこの頃は蒸気機関の自動車のほうがスピードも出ていました。スタンレースチーマーの記録した205.4km/hは時速200キロを公式に超えた歴史的瞬間でもありました。まだ当時はガソリン車がそこまでスピードの出ない時代で、実際にガソリン車が200km/hを超えるのは1909年のことです。
その後も自動車レースは各国で行われるようになり、同時に、エンジンをはじめとした自動車技術の発展に大きく貢献していくことになります。現在のアルファロメオ(イタリア)やメルセデスベンツ(ドイツ)、ベントレー(イギリス)などが国の威信をかけて参加していたのです。
結果を残すためとはいえ、それは自然と自動車の発展を促すこととなりました。
高級車では、6気筒エンジンを搭載したイギリスのロールス・ロイス40/50HPシルバーゴースト(1906年)やアメリカのキャデラックモデル30(1912年)、フランスのイスパノ・スイザ32CV(1928年)などが登場。当時の技術をフル装備させた車両は、一般市民の憧れになっていくのです。

12気筒:8000CC、乗用車のエンジン
海外では自動車を作るだけでなく、その性能向上まで注目されていますが、日本に自動車が入ってきたのは明治31年(1898年)のことです。フランスの軍用車両メーカー、パナール社の作るパナール・ルヴァ(ッ)ソールが日本へ初上陸、その三年後には「山羽式蒸気自動車」と呼ばれる国産第一号の自動車が作られました。
制作にあたったのは山羽虎夫、岡山で電機工場を経営していました。当時はまだ内燃機関ではなく蒸気機関の自動車でしたが、エンジンの性能は良好だったそうです。山羽式蒸気自動車は日本の乗り合いバスとして開発されてきましたが、ここで問題が発生します。それは、エンジンではなくソリッドタイヤの性能が悪いということでした。
当時の日本の工業技術ではその問題を回避できず、計画はお蔵入りとなってしまいます。その後、明治40年(1907年)には国産のガソリンエンジン車(タクリー号)も開発、実用化へと結びつけることとなるのですが、まだまだ国での安定した生産には及ばず…。
つまり、日本はエンジン性能を求める以前の問題で苦戦していたのです。本格的な生産がされるようになったのは1925年、白楊社のオートモ号でした。230台が製造されたものの、その後はGM、フォードのノックダウン生産に市場は寡占状態に、白楊社は解散へと追い込まれてしまいます。
白揚社のメイン社員は、現在のトヨタ自動車(当時は前身の豊田自動織機製作所自動車部)へ。昭和7年(1932年)に設立された現在の日産自動車(当時は前身のダットサン商会)と争うように乗用車生産を試みます。
しかし、日本は第二次世界大戦へ向け、戦争の時代へと突入…。軍事用の開発にすべてを奪われてしまいます。赤旗法の成立で、自動車開発が止まってしまっていたイギリスとは事情こそ違うものの、日本はただでさえ遅れていた自動車開発で、さらに遅れを取ることになるのでした。
日本のエンジン開発の話があまり出てこないのは、日本は戦争の影響や工業技術の遅れもあり、戦前は自動車に関して完全なる発展途上だったためです。日本が自動車業界でひと花咲かせるのは戦後のことで、それも外国のノックダウン生産を受注するところから始まります。
戦後の自動車エンジン開発については、また別のコラムにてご紹介します。



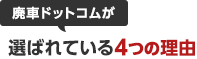
パーツやメタル資源として再利用し国内外に販売!

車解体の資格を持つ廃車.comの工場と直取引だから高く買取れる。

すでに払った31,600円の自動車税も返ってくる。
(4月に廃車/1,600cc普通自動車)